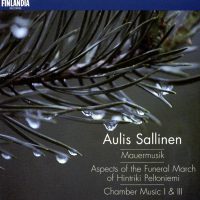9月22日(土)アクロス福岡シンフォニーホールでの、九州交響楽団第370回定期公演の聴きどころを紹介する。私は九響プレイベント「目からウロコ!?のクラシック講座」の担当者だが、このブログの記事は講座の内容を中心に個人的な視点で書いている。したがって内容に関する一切の責任は執筆者にある(譜例はクリックすると拡大表示されます)。
9月22日(土)アクロス福岡シンフォニーホールでの、九州交響楽団第370回定期公演の聴きどころを紹介する。私は九響プレイベント「目からウロコ!?のクラシック講座」の担当者だが、このブログの記事は講座の内容を中心に個人的な視点で書いている。したがって内容に関する一切の責任は執筆者にある(譜例はクリックすると拡大表示されます)。
370回定期公演の演目はマーラー作曲《交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」》。指揮は小泉和裕、出演者はソプラノ:並河寿美・大隅智佳子・吉原圭子、アルト:加納悦子・池田香織、テノール:望月哲也、バリトン:小森輝彦、バス:久保和範、合唱:九響合唱団、九州大学男声合唱団コールアカデミー、NHK福岡児童合唱団MORAI、他の皆さん。
本稿の内容は次の通り。
- 指揮者マーラー
- 妻アルマをめぐる人々
- マーラーの同時代人
- 人間マーラー
- 交響曲第8番変ホ長調
- 第1部「来たれ、創造主たる聖霊よ」
- 第2部「ファウスト:最終場」
なお本稿は九響プレイベント「目からウロコ!?のクラシック講座」(8月30日、アクロス福岡円形ホール)で語ったことを中心に書いている。講座ではネット上のWikipediaなどで知ることのできる履歴や作品リストなどの基礎情報は省いているし、テキストそのものやテキストと音楽との関わりについても詳しくは触れていない。そのことを含みおいて以下を読んでください。
1.指揮者マーラー
 グスタフ・マーラー(Gustav Mahler, 1960-1911)は当時の音楽界では指揮者として有名であった。ウイーン音楽院を卒業後ヨーロッパの様々な歌劇場を渡り歩き、キャリアを積んでいく。結果、1898年のウィーン宮廷歌劇場芸術監督に就任し指揮者の頂点に立つ。この職は同時にウィーン・フィルハーモニーの指揮者であることも意味する。しかしマーラーの指揮者としての楽団員への過酷な要求は楽団員の反発を買う。その反発にはマーラーがユダヤ人であったことも反映していたようで、聴衆のごく一部の反ユダヤ感情も相俟ってマーラーにストレスを与え続けた。
グスタフ・マーラー(Gustav Mahler, 1960-1911)は当時の音楽界では指揮者として有名であった。ウイーン音楽院を卒業後ヨーロッパの様々な歌劇場を渡り歩き、キャリアを積んでいく。結果、1898年のウィーン宮廷歌劇場芸術監督に就任し指揮者の頂点に立つ。この職は同時にウィーン・フィルハーモニーの指揮者であることも意味する。しかしマーラーの指揮者としての楽団員への過酷な要求は楽団員の反発を買う。その反発にはマーラーがユダヤ人であったことも反映していたようで、聴衆のごく一部の反ユダヤ感情も相俟ってマーラーにストレスを与え続けた。
 マーラーは1897年にユダヤ教からカトリックに改宗した。これも信教の必然と言うより、仕事上の軋轢を避けるためであったと言われている。
マーラーは1897年にユダヤ教からカトリックに改宗した。これも信教の必然と言うより、仕事上の軋轢を避けるためであったと言われている。
マーラーが指揮をしている様子のカリカチュアがたくさん残されている。当時は指揮者としてのマーラーの存在感は強烈だったのだろう。残念ながらマーラー指揮による演奏録音は残されていな
2.妻アルマをめぐる人々
 マーラーは1902年に20歳年下のアルマ・シンドラー(Alma Schindler, 1879-1964)と結婚する。アルマは画家の娘であり、ウィーンの芸術家のコミュティの中では美貌の才女として有名で、多くの男性を惹き付けていた。その中で当時もっとも名声を得ていたマーラーを選んだわけだ。
マーラーは1902年に20歳年下のアルマ・シンドラー(Alma Schindler, 1879-1964)と結婚する。アルマは画家の娘であり、ウィーンの芸術家のコミュティの中では美貌の才女として有名で、多くの男性を惹き付けていた。その中で当時もっとも名声を得ていたマーラーを選んだわけだ。
アルマは多才で、特に作曲はツェムリンスキー(Alexander Zemlinsky,1871-1942)に師事し、かなりの才能を見せていたようだ。マーラーはアルマとの結婚に際し「私の音楽をあなたの音楽と思ってくれ」というようなこと宣言して彼女が作曲することを禁じてしまった。ツェムリンスキーは弟子の美貌に惹かれてアルマとの結婚を望んでいたようだが、アルマからはまったく相手にされなかったようだ。なお、ツェムリンスキーは独学の作曲家シェーンベルク(Arnold Schönberg, 1874-1951)の生涯ただ一人の作曲の師として対位法を教えた。

アルマはマーラー在世中に有名な建築家ワルター・グロピウス(Walter Gropius, 1883-1969)と関係を持つ。そのことがマーラーを苦しめ、楽団員との軋轢やその底に見え隠れするユダヤ差別と相俟って精神を病んでしまった。最終的には有名な精神科医ジークムント・フロイト(Sigmund Freud、1856 – 1939)の診断を受けて立ち直った。その際、マーラーはアルマの作曲禁止を解き、そればかりか結婚前に作曲した彼女の作品の出版まで行った。

アルマとグロピウスはマーラーの死後に結婚した。二人の間に生まれたのがマノン・グロピウス(Manon Gropius, 1917-1935)(図8)で、聡明で美しい少女だった。このマノンに惹かれたのが作曲家アルバン・ベルク(Alban Berg, 1885-1935)で、彼はマノンの早すぎる死に衝撃を受け、作曲中のオペラ『ルル』を中断してまでマノンの死を悼むレクイエムとしての《ヴァイオン協奏曲》を一気に書き上げた。この《ヴァイオリン協奏曲》は20世紀のこのジャンルの名作の一つに数えられている。
 アルマとグロピウスの関係はマーラーの晩年に一時中断した。マーラー死後すぐにアルマが関係を持ったのは画家のオスカー・ココシュカ(Oskar Kokoschka, 1886-1980)。彼の《風の花嫁》(下左)はベッドの中のアルマと彼自身とを描いたものだ。アルマへの愛の強烈さの証明のような作品だ。なお、ココシュカには作曲家アントン・ウェーベルン(Anton Webern, 1883 – 1945)(下中)やシェーンベルク(下右)の肖像画も残されている。
アルマとグロピウスの関係はマーラーの晩年に一時中断した。マーラー死後すぐにアルマが関係を持ったのは画家のオスカー・ココシュカ(Oskar Kokoschka, 1886-1980)。彼の《風の花嫁》(下左)はベッドの中のアルマと彼自身とを描いたものだ。アルマへの愛の強烈さの証明のような作品だ。なお、ココシュカには作曲家アントン・ウェーベルン(Anton Webern, 1883 – 1945)(下中)やシェーンベルク(下右)の肖像画も残されている。



アルマをめぐる人間関係を見ると、19世紀末から20世紀初頭のウィーンの激動する社会情勢を背景にしたジャンルを超えた新しい芸術文化の濃密なコミュティの存在を感じる。そうした芸術文化のコミュティを想像しながらマーラーの音楽に接すると、より深くマーラーを理解できるように感じる。
3.人間マーラー
マーラーは指揮者として世界最高の地位であるウィーン宮廷歌劇場芸術監督に就くが心の中には常に鬱屈があった。アルマに起因するものもあるだろうが、自身のアイデンティティに基づくものが大きいと思われる。彼は自身について次のように語っている「私は三重の意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人、ドイツ人の間ではオーストリア人、そして全世界の国民の間ではユダヤ人として」と。このあたりのことは我々日本人には実感としてはよく分からないが、彼の死後わずか30年も経たないうちに起こったナチスによるユダヤ人迫害の現実から想像できることもあるはずだ。
マーラーは自身の成功に奢ることなく、ツェムリンスキーやシェーンベルクなどの若い世代の新しい音楽を理解しようと努めていた。コンサートでシェーンベルクの作品に激しいヤジが飛び交ったりした時にはヤジを飛ばした聴衆に「静かに聴け」と一喝したりしたようだ。シェーンベルクを自宅のサロンに招き入れ激論を交わしたこともあったようだ。激論に対して怒ったマーラーはシェーンベルクを追い出してしまったが、その後にシェーンベルクが訪ねてこないことをいつまでも気にかけていたようだ。シェーンベルクの音楽を「理解はできないが、たぶん正しい方向なのだろう、私はもう老いぼれだ」というような感慨を漏らしたとか。
 有名な歌曲作曲家フーゴー・ヴォルフ(Hugo Wolf,1860- 1903)はウィーン音楽院のマーラーの同級生であり、下宿をシェアしていた仲である。そのヴォルフが後に精神を病み、ウィーン宮廷歌劇場楽長の楽屋に「オレはマーラーだ、オレのオペラを演奏する」と自作オペラのスコアを手に錯乱して乗りみ、マーラーが迷惑を蒙ったことがあったようだ。成功した同級生へのやっかみがあったのだろうか。客観的にはヴォルフも十分に成功した作曲家だったが、梅毒による精神病の症状としての振る舞いであったようだ。後年、ヴォルフの死後、マーラーはそのオペラを上演している。
有名な歌曲作曲家フーゴー・ヴォルフ(Hugo Wolf,1860- 1903)はウィーン音楽院のマーラーの同級生であり、下宿をシェアしていた仲である。そのヴォルフが後に精神を病み、ウィーン宮廷歌劇場楽長の楽屋に「オレはマーラーだ、オレのオペラを演奏する」と自作オペラのスコアを手に錯乱して乗りみ、マーラーが迷惑を蒙ったことがあったようだ。成功した同級生へのやっかみがあったのだろうか。客観的にはヴォルフも十分に成功した作曲家だったが、梅毒による精神病の症状としての振る舞いであったようだ。後年、ヴォルフの死後、マーラーはそのオペラを上演している。
以上のエピソードからマーラーの人間性の一端を知ることが出来る。彼はひじょうに厳しい人である。大変な努力と精進を自らに課し、現世の成功を勝ちとった。しかしその一方に、現世の成功が全てではないこと、また成功は努力だけがもたらすものではないこと、そうしたことに思いをめぐらすことができる豊かな精神の持ち主だったように思う。
4.交響曲第8番変ホ長調
交響曲第8番変ホ長調は1906ー07年に作曲され、1910年9月12日、ミュンヘンにて初演された。その初演は3000人の入場者数を数え、大文化的事件になり、欧州の著名文化人がそこに集まった。
五管編成を基本にハープ3台、オルガン、多数の打楽器を加えた大管弦楽と7人の独唱者、2群の混声合唱と児童合唱の多くの演奏者を必要とする曲である。初演時には演奏者が計1000人を超えていたとか。そこで興業主は「千人の交響曲」と名付けた。ただマーラー自身はこの営業優先の名前を気に入ってはいなかったようだ。
これまでのマーラーの交響曲では第1番が器楽のみ、第2番から第4番までが声楽つき、第5番から第7番までが器楽のみで、第8番がふたたび声楽つきになる。これまでにない大規模編成で、彼は友人の指揮者メンゲルベルクに以下のようにこの曲について述べている。
- 「私はちょうど、第8番を完成させたところです。これはこれまでの私の作品の中で最大のものであり、内容も形式も独特なので、言葉で表現することができません。大宇宙が響き始める様子を想像してください。それは、もはや人間の声ではなく、運行する惑星であり、太陽です」
- 「これまでの私の交響曲は、すべてこの曲の序曲に過ぎなかった。これまでの作品には、いずれも主観的な悲劇を扱ってきたが、この交響曲は、偉大な歓喜と栄光を讃えているものです」
曲の構成は通常の4楽章制交響曲ではなく、2楽章制。楽章(Satz)という用語ではなく部(Teil)という用語を使っている。「第1部:聖霊降臨祭の讃歌」と「第2部:ファウストからの終幕の場」から成っており、「天上へのあこがれ」と「悪魔にさいなまれてきた魂の救済」がテーマになっている。まるでオラトリオか大規模カンタータのような外見だ。
5.第1部「来たれ、創造主たる聖霊よ」
テキストは中世マインツの大僧正フラバスス・マウルス作のラテン語の讃歌(譜例1)である。ドイツ語圏のカトリック信者においてはかなりよく知られた讃歌だそうで、聖霊の降臨を讃える内容で、意味はカトリック信者には自明のこととされている。したがってマーラーがこの讃歌のドイツ語訳を友人に依頼したことが、彼のユダヤ教からカトリックへ改宗の動機に疑念を抱かせる一因にもなっている。
マーラーは自身の音楽表現を優先させて歌詞をかなり大胆に改編している。新たに節を挿入したり、語順や行を入れ替えたりしている。テキストは音楽化のための素材の一つに過ぎないという考えがそうさせている。このテキストの冒頭のオリジナルの旋律と交響曲第8番第1部冒頭の主題旋律(譜例2a)との著しい違いはそのことを示している。
この主題旋律はソナタ形式の「第1主題」に相当する。1小節ごとに拍子を変えるこの旋律の正統的な本来の姿は譜例2bのようになる。変則にされているのはveni(来たれ)の強調のためである。なお動機cは同音反復であり、曲の途中ではそのことを強調するために最初の音を長くしたc’としてしばしば出現する。
主題旋律はトロンボーンのユニゾンによって引き継がれるが、その際、リズムの処理によって別の面が強調される(譜例3)。動機aとbの最初の音を組み合わせた印象的な動機dであり、これは独立してその後に何度も出現する。
第1主題が何度か変奏反復された盛り上がった後に「副第1主題」(譜例4)が出現する。この主題は再現部で第1主題と同時に出現する。
「第2主題」は独唱(第1ソプラノ)によって提示される。第1主題とは対照的になだらかな旋律線を示している(譜例5)。
第2主題はもう1種類存在し、それを「副第2主題」(譜例6a)と名付ける。
この副第2主題はその後の展開部において新たな旋律が継ぎ足されて出現する。その旋律は均衡を破った極めて表現主義的なものである(譜例6b、大譜表の下段)。対旋律には第1主題の変奏(譜例6b、大譜表の上段)が合唱で登場する。
なお音楽における表現主義とは「表現内容が主導的となり、その結果、媒体の形式自体が持つ均衡を破ることによって表現が行われる芸術傾向(略)20世紀初頭の後期ロマン派の中でも特殊な、従来の形式の枠組みやテクストの選択制限を破るような音楽」(柴田南雄『グスタフマーラー』岩波新書、1984、pp.137-138)のことであり、副第2主題の展開に見られるような動機の奔放な変奏反復や音域幅の極端に広い旋律形成、リズムの非段落性などは典型的に表現主義的である。
この曲におけるソナタ形式は図式的な形式であって、提示部おける主題やそれを構成する動機の用いられ方は、まるで古典的ソナタ形式楽曲における展開部のように、安定を知らず、不均衡な状態で主題や動機が配置されている。
必然的にこの曲の展開部は古典的ソナタ形式のそれよりもはるかに多様で複雑である。主題の反転型(譜例7)やそれに主題の縮小形が絡んだりする(譜例8)。
そして既出の動機を用いて新たな主題を形成する(譜例9)。Accende lumen sensibus(私たちの五感に火を灯し)の歌詞から「灯火の主題」と名付ける。灯火の主題の動機eは第2部において重要な動機となる。
この曲における動機の展開は多種多様で、そのすべての聴取理解は不可能である。圧倒的大音量の迫力満点の音楽的推移はその聴取理解がなくても聴き手を感動に導いてくれる。しかしその裏には精緻な動機展開が網の目のように張り巡らされていることを忘れてはならない。それは例えば訪れた者を感動に導く大規模な教会建築に似ている。そうした教会建築は全体に精緻な造形や彫像が施されているが、それらをすべて直接見ることは不可能だ(天井近くの壁の装飾や屋根の上の彫像は目にすることがない)。しかし精緻な造形や彫像が施されているという事実の存在が、たとえそれを目にすることがなくても、感動をもたらすのである。
6.第2部「ファウスト:最終場」
第2部はゲーテの原作「ファウスト」の最終幕をテクストにしておりドイツ語で書かれ、「人間の諸罪悪からの救済」が描かれている。
休みなしで演奏される1時間弱の演奏時間を要する長大な楽章で、形式的な把握は難しい。そこで形式的把握を目指すのではなく、頻繁に出現する主題・動機をあたかもワーグナー楽劇の示導動機のように捉えてその出現を追いかけて聴く方の方が曲の素晴らしさを実感する。主題の名称は筆者が適当につけたものである。
第1区分(Poco Adagio)は器楽だけで演奏され、山間の谷、深い森、岩だらけの荒涼としたファウスト最終場の様子が描かれる。冒頭に第2部における複数の主要動機がはっきりと提示される(譜例10)。まず高音弦楽器のトレモロに導かれて低音弦楽器がピッチカートによって動機aと動機eの縮小形を提示する。その後に動機fを含む旋律主題をフルートとクラリネットが高音域で提示する。この主題を後に出てくるテキストの内容からこれを「恍惚の主題」と名付ける。この恍惚の主題の後半部の動機eは第1部の灯火の主題にすでに存在している。動機fは第2部の主要動機であり、この動機fを耳が追いかけていくだけでも第2部は十分に楽しめる。
やがて動機fと動機eが静的に展開されていく過程で対旋律として劇的な主題が現れる(譜例11)。後に出てくるテキストの内容から「深淵の主題」とする。この主題は冒頭の跳躍上行音型と後半のなだれ落ちるような跳躍下行音型の連続に特徴があり、音楽進行上の盛りあがりを刺激する。第1部分の副第2主題との関連が示唆されるまさに表現主義的な内容である。
この区分を閉める際に動機fを用いた「天使の主題」(譜例12)が登場する。後に天使たち(女声合唱)によって歌われる。
第2区分(Wieder langsam)は第1区分の反復的な内容の音楽であるが、合唱や独唱が加わり、表情がよりダイナミックになる。はじめに男声合唱が動機fを用いて場の情景を歌う(譜例13)。
バリトン(恍惚の神父)が恍惚の旋律主題(譜例14)を永遠へのあこがれの言葉によって歌う。バス(深淵の神父)が深淵の主題を全能の創造主への怖れの言葉によって歌う。その表情はより劇的なものになっている。
第3区分(Allegro deciso)は天使たち(女声合唱)が灯火の主題を、児童合唱が天使の主題を喜ばしくうたう。その後、高音木管楽器で天上の世界の喜びを伝えるような軽やかなテンポの楽句を示す(譜例15)
やがて、完全に近い天使たち(混声合唱)が第1部分の展開部の冒頭と同じ音楽(譜例6b)を「私たちには地上の残滓がまとわりついている」と歌う。やがて若い天使たち(女声合唱)が天使の主題によって霊的な存在を讃える。
第4区分(Äußerst langsam, Adagissimo)はヴァイオリンの高音域のゆったりとした旋律(譜例16)で始まる。この後の歌詞の内容から「栄光の母の主題」と見なす。
この主題にあわせて男声合唱がおごそかに神を讃美し始める。ソプラノII(悔悟する女)、ソプラノI(罪深き女)、アルトI(サマリアの女)、アルトII(エジプトのマリア)も順に讃美する。やがて舞台とは異なる高い場所にいるソプラノIII(栄光の聖母)が「一層の高みに昇ってきなさい」と透明な感じで歌う。
第5区分(Hymnenartig)はハープとオルガンの伴奏でのテノール(マリアを崇める博士)のマリアへの讃歌によって始まる。さらに恍惚の旋律主題を歌う。
第6区分(Sehr langsam beginned)は合唱による恍惚の旋律主題で静かに始まる。やがてこれまでに登場した主題や動機などが次々に登場して徐々に盛り上がり、大音量のクライマックスにいたる。最後に舞台とは別の場所にいる金管楽器合奏によって第1部第1主題、特にその動機d(譜例3)が圧倒的な音量の中で天への呼びかけとして聞こえる。