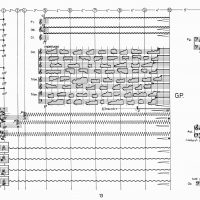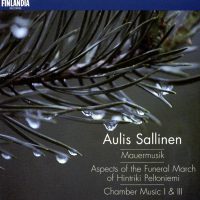10月15日(日)アクロス福岡シンフォニーホールでの、九州交響楽団第362回定期公演の聴きどころを紹介します。九響プレイベント「目からウロコ!?のクラシック講座」の担当者ですが、このブログの記事は自由に個人的な視点で書いています。したがって内容に関する一切の責任は執筆者にあります。(譜例はクリックすると拡大表示されます)
10月15日(日)アクロス福岡シンフォニーホールでの、九州交響楽団第362回定期公演の聴きどころを紹介します。九響プレイベント「目からウロコ!?のクラシック講座」の担当者ですが、このブログの記事は自由に個人的な視点で書いています。したがって内容に関する一切の責任は執筆者にあります。(譜例はクリックすると拡大表示されます)
演奏曲目
- フェリックス・メンデルスゾーン/交響曲第5番ニ長調作品107「宗教改革」
- カール・オルフ/世俗的カンタータ「カルミナ・ブラーナ」
指揮者は九響の音楽監督である小泉和裕。「カルミナ・ブラーナ」の独唱陣はソプラノ:安井陽子、カウンターテナー:藤木大地、バリトン:青山貴、合唱は横田諭指揮の九響合唱団、児童合唱は久留米児童合唱団です。
このコンサートにおけるメンデルスゾーン「宗教改革」とオルフ「カルミナ・ブラーナ」という上演曲目の組み合わせはたいへん興味深いものです。主催者にはその意識はなかったようなのですが、1933年から1945年までのナチス政権下で上演を禁止されていた作曲家と、対照的にその当時に頻繁に上演されていた現代作曲家の作品による組み合わせだからです。
メンデルスゾーンはユダヤ人です。ご存じのようにナチス政権下ではユダヤ人が迫害・追放・虐殺され、彼らの作品の上演も禁止されました。おまけにナチスは当時の現代音楽を退廃芸術として上演禁止にし、ユダヤ人でなくてもパウル・ヒンデミット(1895-1963)やカール・アマデウス・ハルトマン(1905-1953)などの当時の才能ある作曲家は国外へ亡命するか、表だった活動を一切自粛していました。その中でカール・オルフの《カルミナ・ブラーナ》は大衆にも親しめる現代作品として、ドイツを代表する同時代の音楽芸術として、ナチス政権はその上演を奨励したのです。本来ならば《カルミナ・ブラーナ》はナチス政権の負の刻印が押されて第2次世界大戦後は評判を落としたはずなのですが、そうはならなかったのです。そのことはこの作品が真にすぐれた芸術性を持っていることの証明です。
フェリックス・メンデルスゾーン/交響曲第5番ニ長調作品107「宗教改革」
- 作曲:1830年、初演:1832年11月、ベルリン・ジングアカデミー奏楽堂、作曲者指揮
メンデルスゾーン、経歴
フェリックス・メンデルスゾーン(1809 – 1847)はプロテスタント(福音派)に改宗した裕福なユダヤ人の銀行家の家庭に育ち、音楽のみならず幅広い分野において英才教育を受けました。幼いころから多くの文化人と知り合い、12歳の時にはワイマールのゲーテの邸宅を訪ね、彼の前でピアノを弾いています。かつてモーツァルトのピアノ演奏も聴いたことのあるゲーテは、メンデルスゾーンのそれがモーツァルトよりも優れていると評価したと言われています。
彼は早くから作曲家・演奏家(特に指揮者)としてその才能がひじょうに高く評価されていました。活躍の場はドイツだけにとどまらず、国外からの招聘も多く、イギリスには10回も訪れ演奏活動をおこなっています。メンデルスゾーンも当時の芸術家のあこがれの地であるパリよりもロンドンを高く評価し愛していました。
バッハのマタイ受難曲の復活上演や、当時シューマンがその草稿を発見したシューベルトの第8交響曲「グレート」の価値を認めて初演するなど、音楽を学術的にとらえる能力もメンデルスゾーンは卓越していました。したがって実力が正当に要求される職、たとえばライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者やライプツィヒ音楽院の校長職務などにおいては重用されていました。反面、ベルリン・ジングアカデミー指導者の職に選ばれなかったり、1830年の宗教改革300年を記念して作曲した交響曲第5番「宗教改革」が記念行事には演奏されなかったりなど、実力よりも名誉が重視される局面においてはユダヤ人であるがゆえの差別を受けたと考えられています。
作曲の契機
交響曲第5番はメンデルスゾーンの2番目の交響曲として1830年に作曲されました。宗教改革300年記念行事において演奏されなかったのは作曲の遅れが原因であったとか、カトリック教会の抵抗で記念行事自体が中止されたとかと言われてきましたが、最近の研究によると、かならずしもそうではなかったようです。
この曲、結局のところ生前にはたった1回しか演奏されず、出版は死後になされました。交響曲番号が実際の作曲順を反映していないのはそのためです。この曲の生前のたった1回の演奏というのは、この曲の魅力を考えるとちょっと考えられません。親の代に改宗したばかりのユダヤ人の手による作品ということが周りの人たちの心理的抵抗を呼び起こしたのでしょうか。あるいはメンデルスゾーン自身がこの作品に入れ込みすぎて、作曲時の熱が醒めた時に、この曲に満ちている激情に自ら否定的評価を下してしまったのかも知れません。
標題との関係はドレスデン・アーメン(讃美歌567番Ⅲ、譜例1)やルター作曲の讃美歌「神はわがやぐら」(讃美歌267番、譜例2)が曲中に登場することに明白です。それ以外の関係をメンデルスゾーン自身は特に記していませんが、宗教改革をめぐる歴史とそこから喚起された感情を聴き取ることは可能です。
構 成
第1楽章はニ長調の穏やかな序奏と火のように激しいニ短調の主部から成っています。主部はソナタ形式です。改革への意思とそのための情熱的行動を暗示していると考えられます。
ドレズデン・アーメンは序奏の最後に静かに2回現れます。
主部の第1主題は激しい情熱を表しています。跳躍上行音型と順次下行音型とが交互に現れます(譜例3)。まるで「改革に挑んでは弾圧される」という運動を象徴しているかのような旋律線の構造です。第1主題後半には跳躍のための助走のような減七分散下行上行音型が現れます。
第2主題はなだらかな旋律線を描きます(譜例4)。イ長調ですが、音階の第6音が半音下行した和声的長音階を用いており、単純な明るさは影を潜めています。宗教改革運動における一瞬の躊躇の思いと、その思いの克服を表しているかのようです。
第2楽章は快活なスケルツォです。農民のダンスを思い起こさせます。宗教改革が農民を中心とする庶民に支えられ、まさに庶民のためになされようとしていることを暗示しているかのようです。
第3楽章は甘すぎるほどの音楽であり、静かですが、敬虔な祈りという感じはしなくて、非常にエモーショルな祈りを表しています。私にはメンデルスゾーンの個人的な複雑な宗教感情の発露のように思えます。
第4楽章は宗教改革が成った喜びの音楽のように思います。序奏では静かに演奏される「神はわがやぐら」(譜例5)が主部ではフーガ風の主題に変形されて対位法的音楽を展開します(譜例6)。この楽章はマタイ受難曲復活上演の経験が反映された音楽であり、バッハへのオマージュのように聞こえます。
第1主題は2オクターブ以上の音域を上行し下行する旋律で、人間の声では表現できない音域幅を用いており、祝福する神の声を象徴しているかのように聞こえます(譜例7)。最後は「神はわがやぐら」が壮大に奏されて、この交響曲がルター讃歌でもあることを高らかに宣言するのです。
カール・オルフ/世俗的カンタータ「カルミナ・ブラーナ」
- 作曲:1935 – 36年、初演:1937年、フランクフルト歌劇場
オルフの経歴、音楽的特徴
カール・オルフ(1895 – 1982)はバイエルン州の首都ミュンヘンに生まれ、育ち、ミュンヘン音楽大学で学び、教え、その地で86歳の生涯を閉じました。若い時には劇場の指揮者としてミュンヘン以外のいくつかの都市で働いていました。
バイエルンはドイツ連邦の中の最大の州で、歴史的・文化的・住民の気質的にあたかも独立国のような存在です。その独立性は、たとえば現在ドイツの政権与党CDU(キリスト教民主同盟/Christlich-Demokratische Union Deutschlands)は、バイエルン州においてのみCDS(キリスト教社会同盟/Christlich-Soziale Union in Bayern)と名乗っていることなどに現れています。
バイエルンは芸術面においては保守的な傾向が強いと言われています。オルフも作曲活動を開始して以来、保守的傾向によって全ドイツ的には地味な評価しか受けていませんでした。その評価を一転させたのが1937年に発表された「カルミナ・ブラーナ」です。今やテレビや映画、イベントなどのBGMとしてこの曲の冒頭を耳にしたことのない人はたぶんいないでしょう。芸術音楽としての高い評価を得るとともに、これほど広く大衆的人気を得ている20世紀の音楽はこの曲以外にはありません。
高い評価を受けた理由はこの曲が中世・ルネッサンス音楽と密接に関連したアルカイック趣味を臆面もなく示している点にあります。単純な旋律線や変化のない音型反復、単純な和声、対位法の欠如、あからさまな拍節的リズムなど、これらは当時の最先端の動向とは真反対です。最先端の徹底した否定は、それゆえに最先端になり得るのです。
ただ、アルカイック趣味は管弦楽法には及んでいません。リズム打楽器の派手な使用やピアノの打楽器的扱いなどは当時先端を走っていた作曲家ストラヴィンスキーのバレエ曲、特に「結婚」(1923)の技法を積極的に取り入れています。リズムの点においてもストラヴィンスキーの影響は顕著で拍節的ではありますが混合拍子の使用が目立ちます。
オルフは「カルミナ・ブラーナ」の大成功を機にそれ以前の作品を破棄します。それ以前の作品は後期ロマン派的作風とドビュッシーの印象派的作風の影響を受けたものだと言われています。破棄は自己の作風を特徴付けるための措置なのでしょう。その後、オペラ「月」(1938)「賢い女」(1941)、カンタータ「カトゥーリ・カルミナ」(1943)など「カルミナ・ブラーナ」と同様の特徴を持つ作品をつくり続けていきます。
作曲の契機
曲名の「カルミナ・ブラーナ」は「ボイエルンの歌」を意味するラテン語です。19世紀はじめにミュンヘン近郊のベネディクト派ボイエルン修道院で発見されたラテン語や古ドイツ語などによる歌集(写本)の名前でもあります。11世紀から13世紀の間に放浪学生や流浪僧、吟遊詩人などによって書かれたものです。内容は酒や恋、性、社会に対する不満へのパロディなどの世俗的なものです。この本を1934年に入手したオルフは狂喜します。人間の行動・認識の原型がそこに見られたからでした。また、それがその時代の日常語ではなかった点で、その内容のあからさまな卑俗性を覆い隠し、それを昇華することもできるものであったからです。
オルフはそこから24のテキストを選び、それを4つの部分に分けて曲をつけました。
構成・構造
曲は序「運命の女神フォルトゥナ、世界の女神よ」、第1部「はじめての春」「草原にて」、第2部「酒場にて」、第3部「愛の宮廷」の4部から成る。
序(1〜2)ではまず「運命の女神フォルトゥナ、世界の女神よ」であるフォルトゥナへの怖れを歌います。「1.フォルトゥナよ」の冒頭はこの曲のもっとも有名な部分です。この部分の素材は2つです。aとb1です(譜例8)。b1自体もaを3度上げたもので、基本的には同じです。 これらが次のように組み合わされて出てきます。
Intro – a – a – b2 – a – a – b1 – b2 – a’– a’- b’1 – b’3
ちなみにa’はaのオクターブ上での演奏を意味します。これを見ると先述した「単純な旋律線や変化のない音型反復、単純な和声、対位法の欠如、あからさまな拍節的リズムなど」の特徴が明白です。
第1部前半(3〜5)は「はじめての春」、後半(6〜10)は「草原にて」と題して、生きること、愛すること、自然を愛でることの喜びを歌います。たとえば「4.太陽はすべてを穏やかにする」のバリトンソロは春の到来とともに恋の予感に浸る単純な素朴な旋律が若者の新鮮なときめきを歌います。そこにも先述の特徴が明白です。(譜例9)
第2部(11〜14)は「酒場にて」と題して、身の不遇や、酔っ払っての愚痴、贋坊主の説教の様子などを歌います。「12.私はかつて湖に住んでいた」では料理に供された白鳥に仮託して哀れな境遇をテノールが酔っ払って歌います。酔っ払い風歌唱が聴きどころ。「13.私は悦楽郷の大修道院様だ」では酔っ払いのバリトンが修道院長のマネをして本来の修道士の行為とは正反対の行為を讃える。バリトンの大げさな説教調子が聴きどころ。「14.酒場にいるとき」では男声合唱がまるで愚痴を吐き続けるようなつぶやきを続け(譜例10a)、突然声高に愚痴をまき散らしたりする(譜例10b)。合唱が酒場で飲んだくれた男たちを表現するところが聴きどころです。
 譜例10a:「14.酒場にいるとき」の愚痴をつぶやき続ける男声合唱
譜例10a:「14.酒場にいるとき」の愚痴をつぶやき続ける男声合唱
![]() 譜例10b:「14.酒場にいるとき」に突然声高に愚痴をまき散らす
譜例10b:「14.酒場にいるとき」に突然声高に愚痴をまき散らす
第3部(15〜24)の「愛の宮廷」は失恋の痛手を受けたある男が新たに美しい乙女に出会い求愛し、最初は躊躇していた乙女もそれに応じるという内容が歌われています。「17.娘が立っていた」では可憐な乙女の高まる期待と溜息とが巧みに表現され、「21.とまどう心の天秤の上で」では性愛への関心が大胆に歌われ、ソプラノの声に心沸きたつものを感じさせます。
最後に“結”(25)として冒頭の曲が再現されます。
カンタータとしてのこの曲の特徴は独唱パートの表情が非常に演劇的であることです。例えばテナーが酔っ払いを、バリトンが説教師を、ソプラノが愛に歓喜する乙女などを演じ歌ったりする箇所がそうです。そこでこの曲は歌い手に衣裳を着せ、バレエやオペラの舞台形式で上演されることが時々あります。舞台には、運命の女神フォルトゥナが地上の人々の運命を定め告げるための車輪が象徴的に提示されることが多いようです。
筆者はオルフの孫弟子
なお、じつは筆者はカール・オルフの孫弟子にあたります。筆者が1973〜77年に日本で師事した作曲家・愛知県立芸大教授の石井歓(1921-2009)はオルフのおそらく唯一の日本人弟子、1974〜76年にドイツで師事した作曲家・国立ミュンヘン音大教授のウィルヘルム・キルマイヤー(Willheln Killmayer, 1927-2017)は戦後はじめてのオルフの弟子でありました。両者とも作風はやや異なりますが、オルフの音楽的個性としての「音型反復」を同じように構成の主要手段として用いている点では、まさにオルフの後継者であるのかも知れません。(譜例11、12)
筆者自身はオルフの影響などは皆無だと思っておりましたが、この稿を書くために自分の作品を見なおしてみると知らずに影響を受けていたようで、昨年に小泉和裕氏指揮の九州交響楽団によって演奏された「聖なる旅立ちー交響曲第5番」にもその痕跡がいくつかありました(譜例13)
 譜例12:ウィルヘルム・キルマイヤー「交響曲第3番(Menschen-Los)」(1973)
譜例12:ウィルヘルム・キルマイヤー「交響曲第3番(Menschen-Los)」(1973)
 譜例13:中村滋延「聖なる旅立ちー交響曲第5番」(2014)第4楽章
譜例13:中村滋延「聖なる旅立ちー交響曲第5番」(2014)第4楽章